手元供養とは?種類・費用・遺骨の扱いまでわかりやすく解説
- 供養/埋葬
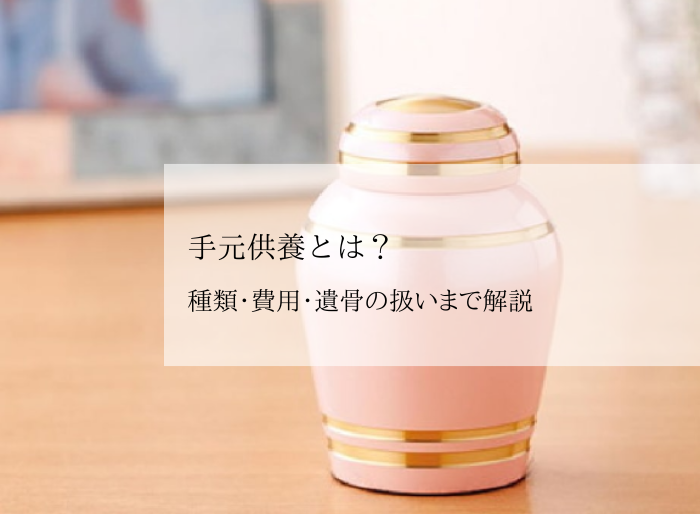
近年「お墓を持たずに供養したい」「家族のそばで故人を感じていたい」と考える方が増え、手元供養という新しい供養の形が注目を集めています。
従来は火葬後に全骨を納骨堂や墓地へ埋葬するのが一般的でしたが、現代では分骨して一部を自宅で保管したり、ペンダントや仏具として身につける選択肢も増えてきました。
本記事では、「手元供養って何?」「どんな種類があるの?」「費用はどれくらい?」「残った遺骨はどうするの?」といった疑問にやさしく解説します。納骨・散骨・永代供養の選択肢も交えて、納得のいく供養を一緒に考えていきましょう。
手元供養とは?意味と目的を知る

手元供養は、「お墓に遺骨を納める」という従来の考え方にとらわれず、故人を身近に感じながら供養する現代的なスタイルです。ここでは、手元供養の基本的な意味や広がりの背景について詳しくご紹介します。
手元供養の基本的な意味
手元供養とは、ご遺骨や遺灰の一部を自宅に安置し、日々故人を偲ぶための供養の方法です。火葬後に分骨して、小さな骨壺やアクセサリーなどに納めるケースが一般的で、最近では仏壇やインテリアとしても違和感のないデザインも増えています。
法的にも許可されており、「納骨=墓地」という考え方にとらわれず、ご家族が自分のペースで供養できることが魅力といえます。
なぜ今「手元供養」が選ばれているのか
近年、核家族化や都市部への移住が進む中で、「お墓が遠くて通えない」「後継者がいない」といった理由から、手元供養を選ぶ人が増えています。また、ペットの手元供養も人気で、家族としての絆を大切にする供養の形が注目されています。
故人を身近に感じたい、日々手を合わせたいという気持ちに寄り添える柔軟な供養方法として、幅広い世代に支持されています。
墓じまい・核家族化との関係性
「墓じまい」に伴ってご遺骨をどうするか悩む方も少なくありません。ご遺骨のすべてまたは一部を手元に残す「手元供養」を選ぶ方が増えています。ご先祖様とのつながりを大切にしつつ、お墓の維持管理の負担を軽減できる新しい供養の形です。
手元供養は、現代の暮らし方や家族構成の変化に柔軟に対応できる“新しい供養のかたち”ともいえるのです。
手元供養の種類とその特徴
一口に手元供養といっても、骨壷やアクセサリー、仏壇型などそのスタイルはさまざま。ご自身の暮らしや想いに合った形式を選ぶためにも、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
ミニ骨壷(分骨)タイプ

もっともオーソドックスな手元供養が、小さな「ミニ骨壷」にご遺骨を収めるスタイルです。陶器やガラス、金属など素材も多彩で、モダンなデザインから伝統的な仏具風まで幅広く選べます。リビングや寝室に置いても違和感がないよう設計されており、日々のお参りがしやすいのが特長です。
遺骨ペンダント・ジュエリータイプ

ご遺骨の一部や遺灰を、ペンダントやリングなどのアクセサリー、ジュエリーに加工して身につける方法です。「いつも一緒にいたい」という想いを叶えられるとして、若い世代や女性に人気があります。密閉構造や防水加工が施された商品も多く、日常使いにも安心です。
仏壇・モニュメント型タイプ
写真
コンパクトでモダンな「現代仏壇」や、石や木で作られた「モニュメント型」は、家具やインテリアに馴染むデザインが特徴。部屋の中で自然に存在できる供養空間を演出したい方に選ばれています。中にはミニ骨壷を内部に収納できるタイプもあり、見た目以上の機能性も備えています。
カプセル型・ガラス製・陶器製など素材別の違い
素材によっても印象や扱いやすさは異なります。
- 【カプセル型】:携帯用に便利。バッグなどに忍ばせて持ち歩けます。
- 【ガラス製】:透明感が美しく、インテリア性も抜群。
- 【陶器製】:伝統的で温かみがあり、仏具と相性が良いです。
- 【金属製】:耐久性が高く、防湿性もあり保管に安心感があります。
それぞれの特徴を理解し、故人やご家族のイメージに合ったものを選ぶとよいでしょう。
手元供養にかかる費用の目安
手元供養は形式やアイテムによって費用に幅があります。高額な仏壇型から手頃なカプセル型まで、ご家族の意向や予算に合わせて選べるのが特徴です。ここでは、主な種類別の価格帯や、追加で必要となる費用について解説します。
種類別の価格相場
手元供養品の価格は、以下のようなタイプによって異なります。
| 種類 | 価格の目安 |
| ミニ骨壷(陶器・金属) | 3,000円~30,000円 |
| ガラス・陶器製オブジェ型 | 10,000円~50,000円 |
| 遺骨ペンダント・ジュエリー | 15,000円~80,000円 |
| 仏壇・モニュメント型 | 30,000円~200,000円以上 |
シンプルな骨壷であれば数千円で手に入る一方、職人による手作りやオーダーメイド品、天然石などの高級素材を使った製品は価格が上がります。
必要になるその他の費用(送料・加工・文字入れなど)
供養品本体のほかに、以下のような追加費用がかかる場合があります。
- 加工費用(封入・粉骨など):20,000円〜30,000円前後
- 文字入れ・刻印費用:3,000円〜
- 送料(ネット注文時):無料〜数千円
- 専用の仏具や収納用品の購入費用:2,000円〜
粉骨処理や封入を葬儀社・石材店に依頼する場合は、セットプランになっていることもあるため、事前に確認しておくのがおすすめです。
手元供養と一般的な納骨の費用比較
手元供養は、永代供養や墓地に納骨するケースと比べて、初期費用が安く抑えられる傾向にあります。以下は目安となる比較です。
| 供養方法 | 初期費用の目安 |
| 一般的な納骨(墓地) | 50万〜200万円以上(墓石代・管理料含む) |
| 永代供養墓(合祀型) | 5万〜50万円前後 |
| 手元供養 | ~10万円前後 |
最近では、故人の遺志や家族の事情をふまえ、「無理のないかたちで供養を続けたい」と考える人が増えています。
手元供養を含めた様々な選択肢を視野に入れ、家族にとって後悔と無理のない供養方法を選ぶことが大切です。
⇒永代供養墓についてさらに詳しくはこちら
手元供養の進め方|準備から選び方まで
手元供養は、納骨や散骨とは違い、比較的自由なかたちで供養を行えるのが特徴です。とはいえ、初めて取り組む方にとっては「何を準備すればいいの?」「いつ始めるのがよいの?」といった不安もあるはずです。
この章では、手元供養を始める際のタイミング・考え方・供養品の選び方について解説します。
手元供養を始めるタイミング
手元供養を始める明確な「期限」や「タイミング」は決まっていません。多くの方が以下のようなタイミングで検討を始めます。
- 葬儀・火葬後、四十九日法要までの期間
- 納骨を見送ると決めたタイミング
- 墓じまい・改葬に伴う分骨や遺骨の一部保管を決めたとき
- 故人をいつも近くに感じていたいという想いが強まったとき
火葬後すぐに始める方もいれば、数年後に決断される方もいます。大切なのは「自分たちの気持ちに正直に」タイミングを選ぶことです。
宗教的な考え方との向き合い方
手元供養は宗教を問わず選ばれていますが、ご家庭の宗派やお寺との関係によっては、事前の相談が必要な場合もあります。
例えば、浄土真宗や曹洞宗などでは供養の在り方に独自の考え方があるため、「納骨の必要性」や「供養の形式」について一度確認しておくと安心です。
また、ご家族や親族の中で供養に対する価値観が異なることもあります。
「自宅に遺骨を置いておくことに抵抗がある」という意見もあれば、「毎日手を合わせたい」という気持ちもあります。トラブルを避けるためにも、可能な限り家族で話し合ってから決めることをおすすめします。
供養品の選び方とチェックポイント
手元供養の供養品は、種類もデザインも非常に豊富です。選ぶ際のポイントを整理しておきましょう。
1. 素材・耐久性
- 陶器、ガラス、真鍮、木材などの素材があります
- 湿気対策や耐火性があるかを確認するのが大切
2.容量とサイズ
- 分骨か全骨かによって骨壷やアクセサリーの容量は変わります
- 骨壷や仏壇タイプなら、設置スペースに合ったサイズを選ぶ
3. 日常的な使いやすさ
- お手入れがしやすいか
- お参りのしやすさ(仏具の並び、安定性など)
4. デザインと心の安らぎ
- 故人の雰囲気に合うもの、部屋に調和するインテリア性のあるものを選ぶ方も増えています
- 最近では「ミニ仏壇」や「インテリア仏具」と呼ばれる商品も人気です
供養のスタイルに迷ったら…
手元供養は、自宅で大切に遺骨を安置できる一方で、「将来的にどうするか」を考える必要も出てきます。
- 分骨した残りの遺骨をどう納めるか
- 将来、自分が供養できなくなった時にどうするか
そんな時には、永代供養墓や樹木葬、モニュメント葬なども合わせて検討するのがおすすめです。手元供養と合わせて「ご家族にとって最適な供養スタイル」をトータルでご提案しております。
手元供養のメリットとデメリットを徹底解説
近年注目を集める手元供養。故人を身近に感じられる一方で、実際に始める前に知っておきたい利点や注意点があります。このセクションでは、選ぶ際に役立つメリット・デメリットを具体的にご紹介します。
手元供養のメリット|心の拠りどころと自由な供養
○故人を身近に感じられる
遺骨ペンダントやミニ骨壺を通じて、日々の暮らしの中で故人の存在を感じられます。お参りのタイミングも自由で、時間や場所に縛られません。
○費用が比較的リーズナブル
墓地や納骨堂を用意するより費用を抑えやすく、数千円~数万円台で始められることも。葬儀費用の軽減にもつながります。
○宗教・宗派を問わず選べる
仏壇型、インテリア調、ガラス製などデザイン性に富み、自分たちの価値観に合った供養スタイルを選べます。
○引っ越しなど生活の変化にも柔軟に対応
自宅に安置できるため、高齢者の一人暮らしや施設入所、遠方への移住などにも対応しやすいのが特長です。
手元供養のデメリット|家族間の認識や保管のリスクも
○親族の理解が得られにくいことも
「遺骨は墓地へ納めるべき」と考える親族がいると、供養の方針でトラブルになる場合があります。事前の相談が大切です。
○保管環境による劣化リスク
ミニ骨壺は湿気やカビに注意が必要です。密閉性や素材にも気を配りましょう。特にガラス・陶器製は地震や落下対策も必須です。
○将来の納骨先を考える必要がある
手元供養はあくまで“現在の選択肢”。最終的にどうするか(例:永代供養墓、合祀墓など)は家族で話し合っておきましょう。
○法的には埋葬ではない点
手元供養は「自宅での安置」であり、「墓地埋葬法」に定められた埋葬行為ではありません。したがって…
- 市区町村への届け出は不要
- 分骨証明書がないと、のちに納骨できない場合がある
火葬時に分骨証明書を取得しておくと、将来的に霊園や納骨堂に納める際も安心です。
手元供養が向いている人
- 故人のそばにいたい気持ちを大切にしたい方
- 墓じまいや核家族化の影響で納骨先が未定の方
- ペットや家族と同じ場所での供養を望む方
- 宗教や慣習にとらわれない供養をしたい方
最終的にご遺骨をどこかに納めたい方には、永代供養墓や樹木葬、モニュメント葬との併用がおすすめです。
山岡石材店では、北陸エリア(富山・石川・福井)での永代供養・生前契約・墓じまいサポートも行っています。
手元供養後に残るご遺骨の扱い方とその選択肢
手元供養で一部の遺骨を手元に残す場合、残りのご遺骨をどうするかは多くの方が悩まれるポイントです。ここでは、遺骨の「安置先」や「最終的な供養の方法」について、選択肢を整理してご紹介します。
全骨供養と分骨供養の違いとは?
手元供養では、ご遺骨をすべて自宅に安置する「全骨供養」と、一部だけを手元に置く「分骨供養」があります。
- 全骨供養:遺骨すべてを骨壷や仏壇に収めて安置します。宗教的に問題はありませんが、スペースや管理面の配慮が必要です。
- 分骨供養:遺骨の一部だけを手元に置き、残りは寺院や霊園に納骨する方法です。
分骨する際は、火葬場での「分骨証明書」取得が必要な場合があります。また、宗派によっては分骨に対する考え方が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
一部を手元に、残りを納骨する方法
多くの方が選ばれているのが、「一部は手元に」「残りは納骨」という供養スタイルです。
- 家族のお墓へ納骨:すでに代々の墓がある方は、そこへ納骨するのが一般的です。
- 永代供養墓・納骨堂:後継者がいない方や維持管理の負担を避けたい方には、寺院や霊園による永代供養も人気です。
- 本山納骨:宗派の本山で納骨・供養してもらう安心感から、信仰を重視される方に選ばれています。
自然に還す選択肢:樹木葬・散骨
「自然の中に還してあげたい」という想いから、以下のような供養方法を選ぶ方も増えています。
- 樹木葬:墓石の代わりに樹木を墓標とする自然葬。個別型・合祀型があります。
- 散骨:海や山など自然の中へ遺骨を撒く方法。粉骨処理が必要で、業者による代行が主流です。
これらは宗教や地域による制限が少ない一方、後からお参りが難しい点などの注意も必要です。
遺骨の一時預かり・保管サービスを活用する
「今は決められないけど、いずれ納骨したい」と考える方には、一時預かりサービスを利用する方法もあります。
- 寺院や石材店が一時的に遺骨を保管
- 安全な専用保管室で管理
- 保管期間中にじっくり家族と話し合いができる
「どこで一時保管できるかどうか将来の納骨や改葬を見据えて、ご遺骨の行き先を考える第一歩としてご活用ください。
将来を見据えた計画:家族と考える最終的な供養
手元供養は「今、故人をそばに感じたい」という想いに応える方法ですが、将来的にどうするかを事前に考えておくことも大切です。
- 家族や親族と供養方針を共有しておく
- 遺言やメモに「希望する供養の形」を記しておく
- 専門家に相談しながら選択肢を整理する
将来の納骨先として、山岡石材がご案内するモニュメント葬や永代供養墓など、残されたご家族にも安心のスタイルをご提案しています。
手元供養と併用できる永代供養墓の選択肢【富山・石川・福井の事例】
手元供養を選ばれた方の中には、「将来的に遺骨を納める場所も確保しておきたい」と考える方が少なくありません。ここでは、北陸エリア(富山・石川・福井)で手元供養と併用できる永代供養墓の代表例をご紹介します。
▶モニュメント葬|富山・石川・福井

手元供養後の安置先として特に人気なのが、山岡石材が提供する「モニュメント葬」です。中央の石碑を囲むように個別納骨スペースが設けられ、家族の想いを残しながら永代にわたって供養されます。
- 手元供養からの移行がしやすい
- 宗派を問わず誰でも利用可能
- 合祀ではない個別供養で安心
▶想縁|富山・福井
富山:浄土苑(想縁)

富山市の中心部からもアクセスしやすい「浄土苑」は、宗派を問わず受け入れ可能な永代供養墓です。継承者がいなくても安心して利用でき、ご家族に代わって永代にわたり供養が行われます。個別の納骨スペースも整備されており、手元供養と組み合わせて利用する方にも適した選択肢です。
富山:富山市北部霊苑(想縁)

北陸新幹線沿い、国道8号線からのアクセスも良い「富山市北部霊苑」は、ペットと一緒に入れる永代供養墓が魅力です。家族の形にあわせてガーデン墓地やモニュメント型など選べる供養スタイルが充実。明るく開放的な霊苑で、「家族らしい供養」を大切にしたい方におすすめです。
福井:殯と癒やしの墓地公苑夢点々(ゆめてんてん)

福井市足羽に誕生した「夢点々」は、一般墓・庭苑墓・モニュメント葬・樹木葬など、あらゆるニーズに応える永代供養付き墓地公苑です。跡継ぎ不要・宗派不問で利用できるうえ、全区画がペット共葬対応。手元供養を終えた後の納骨先としても、多くの方に選ばれています。
※3施設とも、公式サイトにて詳細を確認・見学予約が可能です。
手元供養に関するよくある質問
手元供養を検討されている方から、実際によく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。初めての方でも安心して準備できるよう、わかりやすく解説します。
Q. 手元供養は宗教的に問題ないのでしょうか?
A. 宗教によって考え方は異なりますが、現代では多くの方が受け入れています。
特定の宗派では「遺骨は速やかに埋葬すべき」とされる場合もありますが、手元供養は“故人を身近に感じながら供養する”という思いから広まっています。実際には、家族や寺院との相談を通じて、柔軟に判断されるケースが増えています。
Q. 手元供養の遺骨は将来どうしたらいいですか?
A. 永代供養墓や樹木葬などに納めるのが一般的です。
最終的にご家族が高齢になった場合や、継承が難しくなったときのために、納骨先を生前に準備しておくと安心です。前述の「モニュメント葬」や「夢点々」などがその例です。
Q. 手元供養は火葬直後でも始められますか?
A. 始められます。
火葬後すぐに分骨し、手元に遺骨の一部を安置することが可能です。ただし、分骨証明書などの書類が必要になる場合もあるため、葬儀社や火葬場での対応を事前に確認しておきましょう。
Q. 生前に準備をすることも可能ですか?
A. もちろん可能です。
近年では、自分自身の供養のかたちを生前に選ぶ方が増えています。手元供養品のデザインや素材、遺骨の行き先まで含めて準備しておくことで、ご家族の負担軽減にもつながります。
Q. 手元供養で残った遺骨を分骨するにはどうすればいい?
A. 火葬場や市区町村で「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。
証明書がないと霊園や納骨堂での受け入れができないこともあるため、火葬直後に申請しておくとスムーズです。
Q. 全骨を手元供養にするのは可能ですか?
A. 可能ですが注意が必要です。
全骨を手元に残すと、将来的に納骨場所の選択肢が限られる場合もあります。一部(分骨)を手元供養に、残りを納骨するという併用スタイルが人気です。
Q. ペットの手元供養もできますか?
A. はい、可能です。
専用のミニ骨壷やアクセサリーなども豊富にあります。「人とペットの供養を同じ場所に」というご相談も増えており、山岡石材ではペットと共葬可能なモニュメント葬などもご案内可能です。
→ ペットと一緒に入れるお墓はこちら
Q. 分骨するには特別な手続きが必要ですか?
A. 分骨には「分骨証明書」が必要な場合があります。
火葬場や自治体によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。証明書があれば、後々の納骨や手続きもスムーズに進められます。なお、証明書が不要な場合でも、遺骨の扱いには十分な配慮が求められます。
Q. 将来的に手元供養をやめたくなったらどうすればいい?
A. 手元供養は一時的な供養方法として選ばれることも多く、将来的に永代供養墓や納骨堂へ納める方も増えています。山岡石材店では、後から納骨できる供養先のご案内や生前相談も承っております。ご自身のライフスタイルの変化に合わせて柔軟に対応できます。
まとめ|手元供養は“想いを形に残す”新しい供養の形
手元供養は、遺骨の一部を自宅で大切に保管し、故人を身近に感じながら日々の暮らしの中で想いを伝えることができる現代的な供養スタイルです。ミニ骨壷や遺骨ペンダント、モニュメントタイプなど、デザインや素材のバリエーションも豊富で、自分らしい形を選べるのが特徴です。
「墓じまい」や「継承者不在」などの理由から、納骨以外の方法を探している方にとって、手元供養は大きな選択肢となります。もちろん、将来的な永代供養先や樹木葬との併用も可能です。
また、分骨や保管の方法、親族との関係性など、事前に確認・検討すべき点もあるため、信頼できる石材店や霊園との連携が欠かせません。
山岡石材店では、手元供養に関するご相談から、永代供養墓「モニュメント葬」や改葬、納骨のご案内まで、ワンストップで対応しています。
故人への想いを大切にしながら、これからの供養のかたちを一緒に考えてみませんか?
Contactお問合せ各種
-
電話でお問合せ
0766-64-3051 営業時間:9:00~17:00 -
メールでお問合せ
-
LINEでお問合せ
-
資料請求
-
コラム

