秋彼岸とは?意味・時期・供養の仕方をわかりやすく解説
- 風習
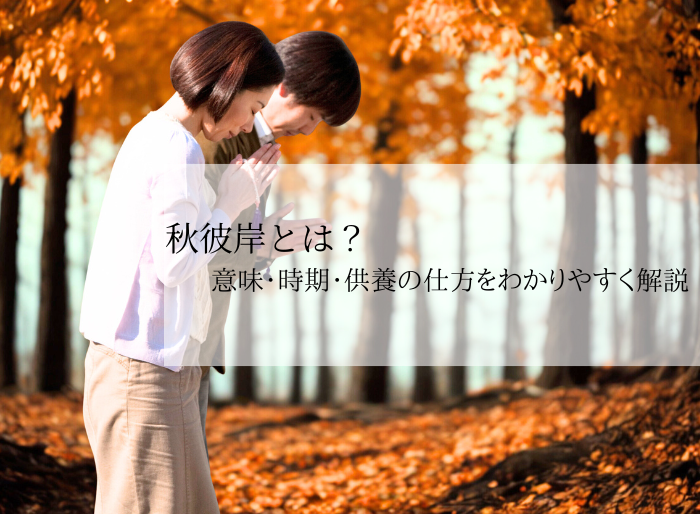
お彼岸は、先祖を敬い、家族の絆を感じる大切な日本の風習です。 なかでも「秋彼岸」は、秋分の日を中心に行われる特別な時期として、多くの方が墓参りや供養を行います。
2025年の秋彼岸は、9月20日(土)〜9月26日(金)の7日間です。
しかし、「秋彼岸って何をするの?」「春との違いは?」「準備はいつから始めればいいの?」と、実は知らないことも多いのではないでしょうか。
この記事では、秋彼岸の基本的な意味から、2025年の日程、供養方法、地域による違いまで、分かりやすく解説します。
秋彼岸とは?その意味と由来
秋彼岸とは、先祖供養のためにお墓参りや仏壇に手を合わせる仏教行事で、毎年9月の秋分の日を中日として前後3日間、計7日間にわたって行われます。
秋彼岸の基本
「彼岸(ひがん)」とは仏教用語で、「迷いや煩悩から解き放たれた悟りの境地」を意味します。
対する「此岸(しがん)」は、私たちが生きているこの世を指し、此岸から彼岸へと心を向ける期間が“彼岸”の意味とされてきました。
春と秋にある彼岸のうち、秋彼岸は秋分の日(昼と夜の長さが等しくなる日)を中心に設けられ、自然のバランスを尊びつつ、ご先祖様への感謝を表す風習として根付いています。
春彼岸との違いは?
春彼岸と秋彼岸は、ともに先祖供養を目的とした行事で、基本的な意味や行動(お墓参り・仏壇の掃除・お供え)に大きな違いはありません。
ただし、季節の違いにより供物や花の種類、過ごし方に変化があるのが特徴です。
- 春彼岸:ぼたもちを供える/桜など春の花を供える
- 秋彼岸:おはぎを供える/萩・彼岸花など秋の花を供える
地域によっても風習が異なるため、地元の文化に合わせた供養を行うことが望まれます。
仏教・宗教的な背景について
彼岸の行事は、仏教の教え「六波羅蜜(ろっぱらみつ)」の実践期間ともされています。
六波羅蜜とは、以下の6つの修行を通じて悟りの境地=彼岸に到達するための教えです。
- 布施(ふせ):施しの心
- 持戒(じかい):規律を守ること
- 忍辱(にんにく):忍耐
- 精進(しょうじん):努力
- 禅定(ぜんじょう):心の安定
- 智慧(ちえ):真理を見極める力
この時期に先祖供養をすることで、自らの心を正し、感謝や思いやりを深めることが仏教的な意義とされています。
秋彼岸はいつからいつまで?
秋彼岸は毎年決まった日付ではなく、「秋分の日」を中心にその年ごとに変動します。
2025年の秋彼岸の日程一覧
秋分の日を中心とする7日間が秋彼岸です。
| 曜日 | 日付 | 意味 |
| 彼岸入り | 9月20日(土) | 彼岸の始まりの日 |
| 中日(秋分の日) | 9月23日(火・祝) | 最も重要な供養の日 |
| 彼岸明け | 9月26日(金) | 供養の締めくくり |
お墓参りに最適な日は?
お墓参りは、以下のような観点で選ぶとよいでしょう。
- 中日(秋分の日):最もご供養にふさわしいとされる日
- 六曜で「大安」や「先勝」の午前中:仏事において縁起が良いとされる
- 家族が集まりやすい日・時間帯:無理なく皆でお参りできる日程
ただし、秋分の日や土日は混雑する傾向があります。
高齢のご家族がいる場合や、ゆっくりお参りしたい場合は、彼岸入り(9月20日)や平日午前中がおすすめです。
秋彼岸に行うこと|お墓参りと供養
秋彼岸はご先祖様に感謝の気持ちを伝え、故人を偲ぶ大切な1週間です。この期間に行う供養やお墓参りには、日々の忙しさでは得られない「心の安らぎ」や「家族のつながり」を感じる時間でもあります。
ここでは、秋彼岸の過ごし方として代表的なものを詳しく解説します。
お墓参りの基本マナーと流れ
秋彼岸に最も大切にされるのが「お墓参り」です。以下のような順序とマナーを意識しましょう。
<お墓参りの一般的な流れ>
- 墓地の入口で合掌・一礼
- お墓の掃除(雑草取り・墓石の水洗い)
- 花・線香・供物を供える
- 合掌・読経・故人との対話
- 最後に感謝を込めて合掌・一礼
掃除はご先祖様への敬意を表す最初の供養です。
また、他の利用者の迷惑にならないよう、持ち込んだゴミは必ず持ち帰ることが大切です。
供花・お供物・お線香の選び方
供えるものにも意味があります。選び方の参考にしてください。
- 供花:菊やカーネーションなどの仏花が一般的。故人が好きだった花を選んでも構いません。
- お供物:果物・お菓子・故人の好物など。常温保存できるものが理想です。
- お線香:香りは好みでOKですが、煙が少ないタイプは他のお参り客への配慮になります。
※動物が食べてしまう恐れのあるもの(生菓子や肉類など)は避け、供えた後は持ち帰るのがマナーです。
自宅での供養や読経の方法
遠方でお墓に行けない方や体調に不安がある場合、自宅での供養も立派な彼岸供養です。
自宅供養の方法例:
- 仏壇をきれいに清掃する
- 線香とロウソクを立てて手を合わせる
- 故人の好きだった食べ物や飲み物を供える
- お経やお念仏を唱える(可能であればお坊さんを招く)
また、彼岸期間中にご家族で集まり、思い出話をすることも立派な供養になります。
秋彼岸のお墓参り|タイミングと準備
秋彼岸の期間中、お墓参りを「いつ・どうおこなうか」は重要なポイントです。ご家族の予定や霊園の混雑状況、高齢者や遠方のご親族への配慮も含めて、計画的に準備しましょう。
ここでは、秋彼岸に最適な墓参りのタイミングと、事前にしておきたい準備のコツをご紹介します。
混雑を避ける時間帯や日程
秋彼岸は、仏教行事の中でも多くの方がお墓参りをする時期です。そのため、以下のような時間帯・日程の工夫で混雑を避けられます。
混雑を避けるポイント
〇ピークは「彼岸の中日(秋分の日)」とその前後の土日
〇平日の午前中は比較的好いていて静かに参拝できる
〇お昼前後(10~13時)は混雑しやすいため、早朝や午後遅めの時間帯がおすすめ
混雑を避けることで、ゆっくりとご先祖様と向き合える時間が得られます。
掃除・草取り・墓石の点検のコツ
秋彼岸は「お墓の大掃除」の時期ともいわれています。ご先祖様への敬意と感謝をこめて、丁寧にお手入れしましょう。
掃除のポイント
- 持参する道具: スポンジ・バケツ・ゴミ袋・軍手・歯ブラシ(細部の清掃用)
- 墓石は水洗いが基本。洗剤は使わず、やわらかいスポンジで汚れを落とします。
- 花立・香立の水垢やカビの除去も忘れずに。
- 雑草が伸びている場合は、根から丁寧に抜くのが理想です。
- 墓石のひび割れやズレがある場合は、早めに石材店へ相談を。
小さなメンテナンスを重ねることで、お墓を美しく保ち、故人も安心して眠れる環境が整います。
秋彼岸を機に見直したいお墓・供養のかたち
秋彼岸は、先祖供養の大切さを再認識する時期であると同時に、これからの「お墓のあり方」や「供養の方法」を見直す絶好のタイミングでもあります。
高齢化・核家族化・継承者問題などを背景に、これまでの「家族墓」に代わる供養スタイルに関心が集まっています。ここでは、秋彼岸を機に検討したい新しい供養のかたちをご紹介します。
永代供養墓や納骨堂の検討

永代供養墓とは、寺院や霊園が遺族に代わって、永続的に供養・管理をしてくれるお墓のことです。お墓の継承者がいない場合や、家族に負担をかけたくないと考える人に選ばれています。
納骨堂は、屋内施設で遺骨を保管・供養する施設。天候に左右されず、管理が行き届いている点が評価されています。都市部では特に人気が高まっており、富山・石川・福井にも設備の整った施設が増えています。
おすすめポイント
- 継承不要、管理が不要なため後の負担が少ない
- 費用も一般墓より抑えられるケースが多い
- 室内型の納骨堂はバリアフリーで高齢者も安心
秋彼岸でお墓参りに訪れた際、「今後のお墓のかたち」について家族で話し合ってみるのも良い機会です。
墓じまい・改葬を考える人が増えている背景
近年、「墓じまい」や「改葬(お墓の引っ越し)」を検討する方が増えています。
墓じまいとは、既存のお墓を撤去して遺骨を別の供養先へ移すこと。改葬は、遺骨の移動に加えて、新たな供養スタイルへ移行する行為を指します。
増加の背景
- お墓のある土地が遠方で管理が難しい
- 子どもが独立して継承できない
- 無縁墓になってしまう不安
秋彼岸は、ご先祖様との対話を通じて、今後の供養の在り方を考える絶好のタイミングです。
→改葬について詳しくはこちら
秋彼岸のタイミングで生前相談をするメリット
最近では、生前のうちに「自分の供養」について考える方も増えています。秋彼岸は、家族が集まる機会でもあり、生前相談を始めるにはぴったりの時期です。
生前相談でできること
- 永代供養墓・納骨堂・樹木葬などの比較検討
- 改葬・墓じまいのスケジュール調整
- 墓石・供養プランの事前契約
- 家族の理解と同意を事前に得る
生前に準備を進めておくことで、遺された家族の精神的・経済的な負担を大きく減らすことができます。
山岡石材店では、北陸エリア(富山・石川・福井)での供養に関する生前相談を無料で承っています。
北陸地方(富山・石川・福井)の秋彼岸の風習
北陸地方には、地域ならではの秋彼岸の風習や供養文化が根付いています。北陸地方では、秋彼岸に仏壇やお墓に備える供物に、地域の特色が反映されることが多くあります。
- 富山県では、落雁(らくがん)や季節の野菜・果物をお供えする習慣があり、稲刈りを控えた秋の収穫に感謝を捧げる意味合いも含まれています。
- 石川県では、金沢の和菓子を供える家も多く、伝統文化と結びついた供養が特徴です。
- 福井県では、精進料理を仏前に供えるご家庭も見られ、昔ながらの風習が今も息づいています。
また、多くの家庭で「ぼた餅」ならぬ「おはぎ」を供えることも定番となっており、地域の味や家族の思い出が詰まった秋彼岸の供養風景が見られます。
秋彼岸に関するよくある質問(Q&A)
秋のお彼岸に関して、よく寄せられる疑問をまとめました。初めて秋彼岸の供養をする方や、改めて意味を知りたい方にもわかりやすく解説します。
Q. 秋彼岸はいつからいつまでですか?
A. 秋分の日を中心に前後3日を合わせた7日間です。
2025年の秋彼岸は、9月20日(彼岸入り)~9月26日(彼岸明け)となります。中心となる秋分の日(9月23日)は、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。仏教では「彼岸=悟りの世界」「此岸=現世」とされ、秋分はこの両者が最も近づく日とされています。
Q. 秋彼岸とはどういう意味ですか?
A. 「彼岸」とは仏教に由来し、ご先祖様の供養を行う期間を指します。
秋彼岸は、仏教行事の一つで、亡き人やご先祖様に感謝し、供養の気持ちを届ける大切な1週間です。語源は「波羅蜜多(はらみた)」=悟りの境地を目指すという意味を持ちます。秋分の日をはさんだ前後7日間に、お墓参りや仏壇での供養を行う風習が日本各地に根付いています。
Q. 秋の彼岸は何を指しますか?
A. 秋分の日を中心とした仏教行事で、春彼岸と対になる行事です。
「秋の彼岸」は、秋分の日を含む7日間(前後3日ずつ)に行われる供養行事を指します。ご先祖様への感謝を込めてお墓参りをしたり、家庭で仏壇に手を合わせたりすることで、心を整え、命のつながりを感じる時間とされています。
Q. 秋のお彼岸のお墓参りはいつがいいですか?
A. 秋分の日を中心に、天気や混雑を考慮して予定を立てるのがおすすめです。
彼岸入り(初日)や彼岸明け(最終日)は比較的空いていることが多く、混雑を避けたい方に適しています。もっとも多くの人が訪れるのは秋分の日当日です。特に遠方から来る方が集中するため、早朝や平日の午前中に参拝すると、ゆったりとした時間が取れます。
Q. 秋彼岸は毎年同じ日ですか?
A. 毎年、日程は変動します。
秋分の日は国立天文台の観測により決まります。その年の秋分の日により秋彼岸の期間も前後するため、毎年カレンダーや公的発表を確認しましょう。
Q. 秋彼岸に喪中でもお墓参りしていいの?
A. 喪中であってもお墓参りに行っても問題ありません。
喪中とは、慶事を控える期間であり、仏事である供養やお墓参りには支障はありません。むしろ、亡き方の霊を慰め、感謝を捧げる大切な時間となるでしょう。
Q. 秋彼岸のお供え物にNGなものは?
A. においの強いもの、生もの、酒類は避けたほうがよいです。
基本的には、季節の花や果物、ぼたもち(秋は「おはぎ」とも)などが一般的です。肉や魚などの生ものは避け、霊園のルールに沿ったお供えを選びましょう。また、お供え物をそのまま放置することもマナー違反となる場合があるため、供養後に持ち帰る「半返し」の考え方も大切です。
まとめ|秋彼岸は「今ある供養」を見つめ直す時間
秋彼岸は、ご先祖様に感謝の気持ちを伝え、家族のつながりを再確認する大切な期間です。秋分の日を中心とした7日間は、現世とあの世がもっとも近づくとされる特別なとき。お墓参りや仏壇の供養を通じて、自分のルーツや命の大切さを見つめ直す貴重な機会となります。
現代では、少子高齢化やライフスタイルの変化により「これからの供養のかたち」を見直す方が増えています。永代供養墓、納骨堂、墓じまい、改葬など、多様な選択肢がある今だからこそ、秋彼岸をきっかけに、ご家族で話し合いの時間を持つのもよいでしょう。
山岡石材店では、富山・石川・福井を中心に、墓地や供養に関するご相談を承っております。秋彼岸の供養方法から、将来の不安、供養の見直しまで、お気軽にご相談ください。
Contactお問合せ各種
-
電話でお問合せ
0766-64-3051 営業時間:9:00~17:00 -
メールでお問合せ
-
LINEでお問合せ
-
資料請求
-
コラム

