墓守りとは?誰がする?いない場合の対処法まで
- お墓
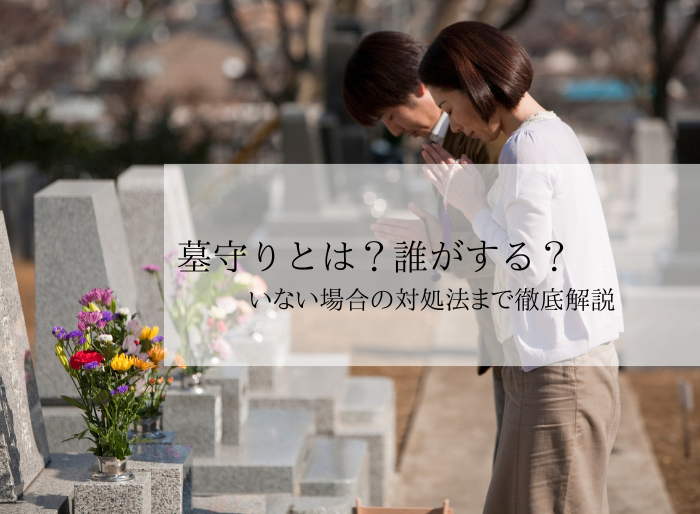
「お墓の管理を誰がするのか?」
近年、少子高齢化や家族構成の変化により、「墓守り」という役割に不安や疑問を持つ方が増えています。
墓守りとは、お墓の掃除をするだけの人ではありません。
ご先祖さまの供養を絶やさず、長く受け継いでいく大切な役割を担う人です。
とはいえ現代では、跡継ぎがいない、遠方に住んでいるなど、従来のように自然と誰かが担うことが難しくなってきています。
この記事では、「墓守りとは何か」から始まり、誰がなるべきか、費用や手続き、もし墓守がいなかった場合の選択肢までを網羅的に解説します。
目次
●墓守りとは?基本的な意味と役割
●墓守は誰がやる?選び方と相続との関係
●墓守りの具体的な役割とは?
●墓守りと墓地管理人の違い
●墓守りにかかる費用とは?
●墓守がいない・できないときの対応策
●墓守を変更したい・引き継ぎたいときの手続き
●よくある質問(Q&A)
墓守りとは?基本的な意味と役割
「墓守り」とはご先祖さまや家族のお墓を日々管理し、供養を続けていく人のことを指します。
“墓守り”の定義(法律上の位置づけ)
法律で「墓守」という言葉の定義はありませんが、実際には「墓地の使用者」や「祭祀承継者(さいししょうけいしゃ)」としての立場が近いとされています。
お墓を所有している人(=使用者)が責任を持って管理し、名義の変更や墓じまいなどの手続きも行います。
特に「祭祀承継者」は民法で定められており、仏壇・位牌・家系図・お墓など、先祖供養に関わるすべてを引き継ぐ人として認められた人です。
墓守りと祭祀承継者の違い(仏壇・お墓)
「墓守」と「祭祀承継者」は同じように使われることが多いですが、実はその役割には違いがあります。
- 祭祀承継者:法律で定められた立場で、仏壇や位牌・お墓などをまとめて受け継ぐ人
- 墓守:主にお墓に関する管理や供養を実務的に担う人(法的定義はなし)
「墓守り」は、法的な制度ではなく慣習的な呼び名といえます。そのため、仏壇は長女が継いで、お墓は次男が管理する、というようなケースも見られます。
実際の運用では、家族間で役割を分けて担うことも珍しくありません。
家制度から個人継承へと変わる墓守りの考え方
かつての日本では、「長男が家とお墓を守る」という“家制度”が当然のように存在していました。
”お墓を継ぐこと=家を継ぐこと”であり、代々の役割として受け継がれてきたのです。
しかし現代では、核家族化や少子化、都市部への移住などにより、その常識は大きく変わってきました。
長男に限らず、子どもがいなかったり、独身のまま高齢を迎える方も増えています。
また、「お墓を守る」こと自体が精神的・経済的に負担になる場合もあり、「そもそも誰が継ぐのか?」という前提が揺らいでいるのが実情です。
そのため、最近では以下のような新しい選択肢が注目されています
- 墓守がいないことを前提とした「永代供養」
- 先を見越して行う「墓じまい(改葬)」
墓守は「自然と誰かがやってくれるもの」ではなく、これからは“意識的に継承・対策を考える”時代になってきているのです。
墓守りは誰がやる?選び方と相続との関係

墓守は、法律で「この人がやらなければならない」と決まっているわけではありません。
墓守を誰がするのかは、相続トラブルの火種にもなりやすいため、できるだけ生前に家族で話し合っておくことが重要です。
家族内での決定方法(長男・配偶者・生前指定)
かつては「長男が墓守をするのが当たり前」とされていましたが、今では家族構成やライフスタイルに応じて、柔軟に決められるようになっています。
配偶者・長女・次男・親戚など、それぞれの事情に合った人が墓守を引き継ぐケースが増えてきました。
また、複数人で役割を分担することも一般的です。たとえば、
- 長女が仏壇を引き継ぐ
- 次男が墓の管理をおこなう
といったように、家族ごとにバランスを取りながら継承されています。
近年では「終活」の一環として、生前のうちに墓守を誰に託すかを明確にする人が増えています。
遺言書に記す、または家族で話し合いの場を持つことで、将来的な行き違いを避けることができるでしょう。
なお、法的に祭祀承継者を指定する場合は、書面による意思表示が必要とされる場合もあります。
とくに相続関係が複雑な場合には、あらかじめ記録として残しておくことが賢明です。
法律で決まっているの?(祭祀財産の承継)
お墓や仏壇、位牌など、先祖供養に関わるものは「祭祀(さいし)財産」と呼ばれます。
これは現金や不動産といった一般の財産とは異なり、相続とは別のルールで承継されるものです。
民法第897条では、祭祀財産についてこう定められています。
「被相続人(亡くなった方)が指定した人が承継する。指定がない場合は、慣習に従って決める。」
つまり、「長男が自動的に継ぐ」とは限らず、本人の意思表示や、家族間の合意が優先されるということです。
誰にも承継されなかった場合には、家庭裁判所が「祭祀承継者」を選任することもありますが、多くの場合は家族の話し合いで決まるのが現実です。
相続トラブルを防ぐために事前に決めておくべきこと
お墓の管理は、財産としての価値があるわけではありませんが、感情や責任が伴うため、相続時にトラブルの原因になりやすいテーマです。
実際には「誰が引き受けるか決まっていない」「管理費や手続きの負担を巡って揉める」といったケースが少なくありません。
こうしたトラブルを防ぐためには、できるだけ生前のうちに話し合い、墓守を誰が担うのかを家族で共有しておくことが大切です。
そして、ただ話すだけでなく、議事録を残したり、遺言書に記載するなど、記録として形に残すことで後の誤解を防ぐことができます。
また、将来的に墓守がいなくなる可能性がある場合には、永代供養や墓じまいといった選択肢も検討しておくと安心です。
「誰かが自然と引き継ぐだろう」ではなく、無理のない形で供養を続けるために、家族での早めの準備と対話が何よりも重要です。
墓守りの具体的な役割とは?

墓守りは「お墓を見守る人」というイメージがありますが、実際には多くの実務的な役割と責任を担っています。
墓地・墓石の維持管理(清掃・供花など)
墓守の最も基本的な仕事は、お墓を常に清潔に保つことです。
定期的に清掃をしたり、草取りや供花・線香のお供えなどを行い、気持ちよくお参りできる環境を整えます。
また、墓石にヒビが入ったり、ズレて傾いていたり、外柵が壊れていたりするような異常にいち早く気づき、必要があれば石材店に修理を依頼する判断も求められます。
近年は地震や大雨などの自然災害による被害も増えており、管理を怠ると倒壊や破損といったリスクにつながることも。そのようなリスク回避も墓守りの役割のひとつです。
法要や年忌の段取り(寺院との調整)
墓守は、命日・お彼岸・年忌法要といった節目の供養を滞りなく行うため、寺院とのスケジュール調整をする役割も担います。
具体的には、僧侶への連絡やお布施の用意、親族への案内や、当日の準備など。法要の中心的な役割を果たすことが多くなります。
最近では、僧侶派遣サービスやオンライン法要といった選択肢も広がっていますが、供養の意思を「かたち」にするという本質的な役目は変わりません。
また、菩提寺がある場合は、檀家としての関係を維持することも墓守の大切な役目のひとつです。
地域によっては護持費や寄付が求められる場合もあるため、その負担も考慮したうえでの承継が必要になります。
墓地の使用者・契約名義人としての責任
多くの霊園や墓地では、墓守が「使用者」として契約名義人になっています。
そのため、名義変更や契約の更新、管理費の支払い、使用ルールの遵守など、さまざまな手続きを担う立場にあります。
特に民間霊園や公営墓地では、契約者が亡くなったまま名義変更を行わずに放置しておくと、将来的に使用権を失う恐れがあります。
場合によっては墓じまいを勧告されるケースもあります。
名義変更には、使用許可証・戸籍謄本・印鑑証明書などの書類が必要になることが多く、煩雑に感じるかもしれません。
しかし、これらの手続きを確実に行っておくことが、将来の安心につながります。
墓守りと墓地管理人の違い
「墓守」と「墓地管理人」は、どちらもお墓に関わる存在ですが、役割や立場はまったく異なります。混同されやすい言葉ですが、それぞれが果たす役目は明確に分かれています。
墓守:墓を守る家族側の立場
墓守とは、ご先祖さまや家族のお墓を個人として管理する人のことです。
清掃・供養・法要の手配、契約管理など、実務面を家族代表として担う立場です。
多くの場合、墓地の使用者として名義登録されており、霊園や寺院との契約や管理費の支払いも墓守が行います。
また、供養の継承者として、先祖を敬い、心を込めてお墓を守っていく役目も担っています。
管理人:霊園や寺院など、墓地全体を維持する運営者
墓地管理人とは、霊園や寺院などの墓地全体を管理・運営する立場の人です。
通路や共用スペースの整備、設備点検、ごみの処理、区画の管理など、墓地環境全体の維持が仕事です。
公営霊園では自治体の指定業者が、寺院墓地では住職や寺務員が管理人になるケースが多く、墓守(使用者)と契約を交わし、管理費を徴収します。
個別のお墓の供養や清掃などは基本的に対象外となります。
役割の境界線と連携の必要性
墓守と管理人は立場こそ異なりますが、お墓を良好な状態で保つためには連携が不可欠です。
たとえば、墓石に異常があった際には墓守が気づき、修繕や対応のために管理人と連絡を取ることになります。
また、霊園によっては、墓守に対して使用状況の確認や定期的な連絡を求めるケースもあり、連絡が取れなくなると無縁墓として扱われてしまう可能性もあります。
それぞれの立場と責任をしっかり理解し、信頼関係を築くことが、安心して供養を続けていくための土台となります。
墓守りにかかる費用とは?

墓守りの役割は、心を込めてお墓を守ることですが、実際にはさまざまな費用がかかります。ここでは、代表的な3つの費用についてご紹介します。
墓地の管理費(年間費用)
墓守が支払う基本的な費用のひとつが「墓地の管理費」です。
これは、霊園や寺院などが行う共用部分の清掃、設備維持、管理業務に充てられる費用で、年に1回使用者(墓守)に請求されます。
管理費は墓地の種類によって異なり、以下が目安です。
墓地の種類 年間管理費の相場
- 公営墓地 3,000円〜10,000円程度
- 民営霊園 5,000円〜15,000円程度
- 寺院墓地 5,000円〜20,000円程度
墓石の修繕・クリーニング代
長年使用している墓石は、雨風や地震、経年劣化により傷みが出てきます。
墓守は、ヒビや傾き、文字の薄れなどの異変に気づいたら修繕の判断をしなければいけません。
よくある修繕費用の目安
- 文字の再彫刻:2万〜5万円
- 墓石の傾き補正:3万〜10万円
- 外柵やカロート(納骨室)の修復:10万〜30万円
お墓のリフォームについては→https://yamaoka-sekizai.co.jp/columns/ohakarifo-mu/
墓守のための交通費や供養費
お墓が自宅から遠い場合は、定期的な訪問に交通費や宿泊費がかかることもあります。
さらに、法要やお彼岸の供養に必要なお布施やお供え物など、意外と多くの出費が重なることも。
これらの費用は一時的なものではなく、継続的な負担として計画的に考えておくことが大切です。
墓を相続する際の税金や固定資産税との関係
お墓や仏壇などの「祭祀財産」は、相続税の課税対象にはなりません(相続税法第12条)。
そのため、相続しても申告や納税の必要はありません。
ただし、墓地の名義変更には書類の提出や手数料がかかる場合があります。
また、墓地が私有地として登記されている場合、例外的に固定資産税が課されることもあるため注意が必要です。
土地や契約の内容を事前に確認しておくことで、トラブルを防ぐことができます。
墓守りがいない・できないときの対応策
現代では、子どもが遠方に住んでいたり、跡継ぎがいなかったりと、墓守ができない家庭が増えています。
このような状況に備えるためには、墓じまいや永代供養、墓守代行などの選択肢を検討しておくことが大切です。
墓じまい(改葬)を検討する
墓じまいとは、現在のお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移すことです。
主に永代供養墓や納骨堂などへの改葬が選ばれています。
基本的な流れ
- 閉眼供養(魂抜き)を行う
- 改葬許可証を取得
- 墓石を撤去・運搬
- 移転先へ納骨・永代供養
墓じまいについて詳しく知りたい方は「墓じまいで後悔しないためには?進め方、費用、トラブル対策を詳しく解説!」をご一読ください。
永代供養墓・納骨堂へ移す
墓守がいない場合に選ばれるもうひとつの方法が、永代供養墓や納骨堂への移行です。
これらは、霊園や寺院が遺骨の供養と管理を代行してくれる仕組みで、後継者がいなくても安心して供養を続けられるのが最大のメリットです。
タイプ 特徴
①永代供養墓 :屋外型。個別 or 合祀。管理不要
②納骨堂:屋内型。個室型が多く、天候に左右されない
③樹木葬・合同墓:自然葬や合同安置。費用が抑えられる
無縁化リスクを避けるための備え
墓守がいないまま放置されると、墓地管理者から「無縁墓」とみなされ、撤去や合祀の対象になることがあります。
これを防ぐには、以下のような事前準備が有効です。
- 永代供養の契約を生前に結んでおく
- 墓守の継承者を文書で指定しておく
- 管理サポート契約を石材店・霊園と締結しておく
「誰も継がないかもしれない」という前提で備えておくことが、家族の負担軽減にもつながります。
墓守りを変更したい・引き継ぎたいときの手続き
ライフスタイルや家族構成の変化により「墓守を別の家族に引き継ぎたい」「自分では続けられないので変更したい」と考える方も増えています。
ここでは、墓守を変更・引き継ぐ際に必要な主な手続きと注意点を紹介します。
墓地使用者の名義変更
墓守を変える場合、まず必要なのが墓地の使用者名義の変更です。
管理者(霊園や寺院)にとって契約者を明確にするためにも重要な手続きです。
※対応や書類は霊園ごとに異なるため、事前の確認が必須です。
また、名義変更には手数料がかかる場合もあります。
墓石の移設や改葬許可申請の流れ
引き継ぎに合わせてお墓の場所を移す場合は、「改葬手続き」が必要です。
遺骨を新しい墓所へ移すには、役所での改葬許可申請が不可欠です。
基本の流れ
①現在の墓地管理者から「埋蔵証明書」をもらう
②改葬先の「受け入れ証明書」を取得
③役所で「改葬許可証」を申請
④墓石の撤去・運搬・新設(石材店に依頼)
改葬には費用も時間もかかるため、親族間での事前相談がとても大切になります。
家族間の合意形成が何より重要
墓守の変更は、法的には一人の意思で手続き可能な場合もありますが、実際には家族全体での合意が不可欠です。
とくに、親族が複数いる場合、「誰が墓守になるか」「費用負担はどうするか」「今後どう供養していくか」など、細かな調整が求められます。
家族内で意見がまとまらないと、墓の放置やトラブルの原因となってしまうため、できるだけ早い段階で話し合っておくことが望ましいです。
必要に応じて、遺言書や合意書などを残しておくと、後々の手続きがスムーズになります。
富山・石川・福井|お墓に関するお悩みはすべて一貫対応

お墓の管理や墓守りに関する不安は、年齢や家族構成の変化とともに増えていきます。
「子どもに負担をかけたくない」「遠方にいて通えない」「墓じまいをすべきか悩んでいる」など、墓守りの継続が難しいと感じる方も少なくありません。
山岡石材店では、富山・石川・福井の北陸エリアにおいて、お墓に関するあらゆるサポートを一貫して行っています。
地元に根ざした石材店として、お客様に寄り添いながら丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。無料相談・資料請求も承っております。
よくある質問(Q&A)
墓守りに関して多くの方から寄せられる疑問を、Q&A形式でまとめました。
実際のご相談や検索ニーズをもとに、実用的でわかりやすい回答を掲載しています。
Q. 墓守りに正式な手続きは必要ですか?
A. 墓守りそのものに法的な登録手続きはありませんが、墓地の「使用者名義変更」や管理費の支払いに関する手続きは必要です。名義を変更する際は、使用許可証や戸籍謄本などの書類が求められます。
Q. 墓守がいないと墓はどうなりますか?
A. 長期間管理されていないお墓は「無縁墓」として扱われる可能性があり、最終的には**管理者判断で撤去・合祀されるケースもあります。**事前に永代供養や墓じまいの検討をおすすめします。
Q3. 墓守りの役目を家族で分担することはできますか?
A. はい、可能です。実際に、仏壇を長女が引き継ぎ、墓の管理を次男が担うなど、柔軟な分担例もあります。ただし、名義人は一人に定める必要があるため、手続き面では代表者の決定が必要です。
Q4. 生前に墓守りの指定や契約をしておくことはできますか?
A. 可能です。生前に祭祀承継者を明確に指定することで、相続後のトラブルを防ぐことができます。また、山岡石材店では生前契約によるお墓の準備・管理サポートも承っています。
Q. 永代供養は墓守り不要ですか?
A. はい、基本的に永代供養墓は管理や供養を霊園や寺院が代行してくれるため、墓守りが不要です。後継者がいない方や子どもに負担をかけたくないという方にとって、有効な選択肢となります。
まとめ|墓守りの負担を減らし、未来の安心を考える
しかし現代では、継続が難しいご家庭も増えており、無理のない形での供養や管理方法を選ぶことが求められています。
この記事では、墓守りの基本から、費用・手続き・不在時の対応までを解説しました。
墓守がいなくても安心して供養を続けられる方法は、確実に存在します。
山岡石材店では、墓守りのご相談から永代供養・墓じまいまで一貫してサポートしております。
「何から始めればいいのかわからない」という方も、どうぞお気軽にご連絡ください。
Contactお問合せ各種
-
電話でお問合せ
0766-64-3051 営業時間:9:00~17:00 -
メールでお問合せ
-
LINEでお問合せ
-
資料請求
-
コラム

